- ★Google+
- ★Hatena::Bookmark
東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科の岩下剛教授と理工学部 機械システム工学科の永野秀明准教授はこのたび、授業再開に向けた新型コロナウイルスの感染症防止対策に関して教室内の換気および飛沫拡散防止についての知見をまとめた。
[本件のポイント]
○新型コロナウイルスの集団感染防止には、3密(密閉、密集、密接)を避けることが重要と言われている。(※)
○新型コロナウイルス感染症は、飛沫や接触により感染することが知られている。(※)
○感染の元となる飛沫について、くしゃみや咳はもちろん、ただ言葉を発するだけでも多くの唾液が飛散していることが確認された。
○密閉空間では、飛沫は室内に留まり、感染リスクが高まることから「換気」が重要となる。(※)
○今後、季節が進むことで頻繁な降雨や気温の上昇が予見されることから、適切な換気の目安が必要となる。
○室内のCO2濃度の測定値から換気・通風の良好の目安を知ることができる。
※厚生労働省サイト( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin )より
東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科の岩下剛教授と理工学部 機械システム工学科の永野秀明准教授はこのたび、授業再開に向けた新型コロナウイルス感染症防止対策に役立てるべく、これまでの研究により得られた知見をまとめた。
岩下教授は、「感染」と「換気」の明確な関係は不明だが、CO2濃度の測定値から、各教室の換気・通風の良好の目安を知ることができるとして、換気の徹底を訴えた。
通常、屋外空気中のCO2濃度は、400~450ppm程度であり、窓や扉を開け放して通風の良い状態(教師1名、児童30名)だと、800ppm程度以下になることが多い。よって、CO2濃度の値をモニタリングしながら、窓開けや扉開けを励行することが望ましいとしている。
春期は窓開けをして過ごせる日も多いが、それでも寒い日や雨の降る日など、常時の窓開けが困難な日がある。また今後、季節が進むことで頻繁な降雨や気温の上昇が予見される。そうした場合には、天候によって適宜調整を行いながら屋外のCO2濃度に近づけることが望ましいとした。
また、永野准教授らは、流体解析による換気効率と飛沫の拡散について評価。その結果、くしゃみや咳はもちろん、ただ言葉を発するだけでも多くの唾液が飛散していること、密閉空間では飛沫は室内に長く留まり、感染リスクが高まることを確認した。
また、環境中に存在する菌類やウイルスのゲノム解析を行った結果、手のひら表面に存在する菌類は、一度物体の表面に触れただけでたやすく移動することが確認された。このことから、ドアの把手や机の表面、食堂の食券機や食器類、テーブルなど、不特定多数の人間が多く触れる場所について、「触れないように工夫する」や「頻繁に殺菌する」など、厚生労働省等が示す対策の有効性を裏付けた。
東京都市大学では、この提言を学内のみならず、世田谷区内と長野県塩尻市にある付属校をはじめとする学校等へも共有し、感染予防に向けた取り組みの強化につなげる。
なお、今回の提案は科研費研究(下記参照)で得られた成果の一部である。
関連科研費研究
研究課題名:インフルエンザ・熱中症対策のための環境維持管理に関する研究
研究代表者:岩下 剛(東京都市大学 建築都市デザイン学部 教授)
研究種目: 基盤研究(B)2019~2021
研究課題名:建築環境マイクロバイオームの実態把握による集団感染機構のモニタリング
研究代表者:加藤信介(東京都市大学大学院総合理工学研究科 客員教授)
研究分担者:永野秀明(東京都市大学理工学部 准教授)
研究種目:挑戦的研究(開拓)2017~2019
(参考)
●新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●建築学会と空気調和衛生工学会の緊急会長談話
https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2020/200323.pdf
○新型コロナウイルスの集団感染防止には、3密(密閉、密集、密接)を避けることが重要と言われている。(※)
○新型コロナウイルス感染症は、飛沫や接触により感染することが知られている。(※)
○感染の元となる飛沫について、くしゃみや咳はもちろん、ただ言葉を発するだけでも多くの唾液が飛散していることが確認された。
○密閉空間では、飛沫は室内に留まり、感染リスクが高まることから「換気」が重要となる。(※)
○今後、季節が進むことで頻繁な降雨や気温の上昇が予見されることから、適切な換気の目安が必要となる。
○室内のCO2濃度の測定値から換気・通風の良好の目安を知ることができる。
※厚生労働省サイト( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin )より
東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科の岩下剛教授と理工学部 機械システム工学科の永野秀明准教授はこのたび、授業再開に向けた新型コロナウイルス感染症防止対策に役立てるべく、これまでの研究により得られた知見をまとめた。
岩下教授は、「感染」と「換気」の明確な関係は不明だが、CO2濃度の測定値から、各教室の換気・通風の良好の目安を知ることができるとして、換気の徹底を訴えた。
通常、屋外空気中のCO2濃度は、400~450ppm程度であり、窓や扉を開け放して通風の良い状態(教師1名、児童30名)だと、800ppm程度以下になることが多い。よって、CO2濃度の値をモニタリングしながら、窓開けや扉開けを励行することが望ましいとしている。
春期は窓開けをして過ごせる日も多いが、それでも寒い日や雨の降る日など、常時の窓開けが困難な日がある。また今後、季節が進むことで頻繁な降雨や気温の上昇が予見される。そうした場合には、天候によって適宜調整を行いながら屋外のCO2濃度に近づけることが望ましいとした。
また、永野准教授らは、流体解析による換気効率と飛沫の拡散について評価。その結果、くしゃみや咳はもちろん、ただ言葉を発するだけでも多くの唾液が飛散していること、密閉空間では飛沫は室内に長く留まり、感染リスクが高まることを確認した。
また、環境中に存在する菌類やウイルスのゲノム解析を行った結果、手のひら表面に存在する菌類は、一度物体の表面に触れただけでたやすく移動することが確認された。このことから、ドアの把手や机の表面、食堂の食券機や食器類、テーブルなど、不特定多数の人間が多く触れる場所について、「触れないように工夫する」や「頻繁に殺菌する」など、厚生労働省等が示す対策の有効性を裏付けた。
東京都市大学では、この提言を学内のみならず、世田谷区内と長野県塩尻市にある付属校をはじめとする学校等へも共有し、感染予防に向けた取り組みの強化につなげる。
なお、今回の提案は科研費研究(下記参照)で得られた成果の一部である。
関連科研費研究
研究課題名:インフルエンザ・熱中症対策のための環境維持管理に関する研究
研究代表者:岩下 剛(東京都市大学 建築都市デザイン学部 教授)
研究種目: 基盤研究(B)2019~2021
研究課題名:建築環境マイクロバイオームの実態把握による集団感染機構のモニタリング
研究代表者:加藤信介(東京都市大学大学院総合理工学研究科 客員教授)
研究分担者:永野秀明(東京都市大学理工学部 准教授)
研究種目:挑戦的研究(開拓)2017~2019
(参考)
●新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省公式サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●建築学会と空気調和衛生工学会の緊急会長談話
https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2020/200323.pdf
▼本件に関する問い合わせ先 |
|
企画・広報室 | |
住所 | : 東京都世田谷区玉堤1-28-1 |
TEL | : 03-5707-0104 |
FAX | : 03-5707-2222 |
大学・学校情報 |
|---|
| 大学・学校名 東京都市大学 |

|
| URL https://www.tcu.ac.jp/ |
| 住所 東京都世田谷区玉堤1-28-1 |
| 「学びたい」という熱意のもとに学生たち自らが中心となって本学の前身である武蔵高等工科学校が創られました。〝公正・自由・自治〞 という建学の精神は、90年の時を経てなお力強く継承されています。 2009年に武蔵工業大学より「東京都市大学」と改称した本学は、現在では社会の根幹を支える理工学をはじめとした環境、情報、都市生活、幼児教育の各分野にわたる、7学部17学科を備える総合大学となりました。本学は、これからも専門的実践教育の伝統を生かし、都市に学びながら、都市の抱える問題を克服できる人材を世に送り出すことで、人類の未来に貢献し、国際都市東京で存在感を示す有数の私大を目指します。 |
| 学長(学校長) 三木 千壽 |
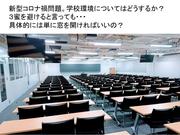

 大学探しナビで東京都市大学の情報を見る
大学探しナビで東京都市大学の情報を見る